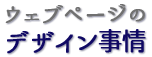2003年4月
ひと昔前はCDと言えば音楽CDのコト。しかし今ではCD-ROM、CD-R、CD-RW、そしてDVD(見た目はCD)と、色々なメディアが登場してきた。DVDと言えば最も新しいメディアのようにも感じるが、実はもう90年代からその技術は確立したいたものが、各メーカーの思惑が複雑に絡んで遅れに遅れたというもの。
さて今では音楽CDでもCD-RWドライブがあれば簡単にコピーを作ることも出来れば、編集してオリジナルのアルバムを作ることもできる。ところが何度も聞きこなしてキズだらけになったCDは、なかなかCD-RWでは読み込めない。音楽CDとPC用のCDとではその機構部分の精度には相当な差があるとのこと。
そのためPC用のCDでは表面にステッカーを貼って重心が狂うことを禁じている。だからCD-R用のラベルは必ずCDの全面に丸いものを貼るようになっている。そうしないと、もしも重心が狂ったまま回転とディスクが崩壊してバラバラに砕け散ってしまうとか。本当だろうか。。
●クリッカブルマップ 2003.4.29
クリッカブルマップは主に地図や路線図で使われることが多いがBBの普及で読み込み速度が向上したことで、これらの用途意外にも使い道が広がってきたようだ。
例えば複数のボタンが並んでいる場合。ロールオーバーで色が変わるような場合は無理にしても、単にリンクするだけであればまとめて1つの画像にしてしまうことが可能になる。
さらにはWordやExcelで予めリンクする文字に色をつけておいて、こいつのスクリーンショットを撮って画像データで貼り付けてクリッカブルマップにしてしまう、などというのも面白い。ただしリンク済みテキストでも色が変わらないが。
ちょっとマニアックだがFORMタグで自動生成されるボタンを一式スクリーンショットにして通常の画像データでクリッカブルマップにするなんてことも。ただし押しても凹まないが。従ってこれはあまり意味がない。
●技術的に優れたページ 2003.4.28
ある会社のHP担当者。サーバも管理しているエンジニアでもあり、かなりの専門知識を持っている。ところがその人が作ったHPは、技術的には優れているものの、デザイン的にはいたって陳腐。
社長がデザインをリニューアルするように指示を出しても、色々と専門的な言葉を並べて今のサイトがいかに優れているかを説明するだけ。
業を煮やした社長はその担当者に秘密でデザインリニューアルを外部のデザイン事務所に発注した。結果Coolでかっこいいページができたのであるが、そのデータをアップロードして管理するようその担当者に命令したところ、へそを曲げた担当者は、その新しいページに色々と文句をつけはじめる。
やれHTMLの記述が間違っているの、JavaScriptの使い方がなっとらんのと。そして必ず言うのがセキュリティーのこと。こんないい加減な作り方では、セキュリティーが保てないと。
まあ、HTMLの書き方が直接セキュリティーに影響する部分は少ないだろうし、HTMLの記述に1ケ所も間違いのないページなんてものを滅多にあるものではない。これはJavaScriptやCSSについても同じこと。
この会社案内のサイトのように、そのイメージをビジュアルで訴求しなければいけない場合は、技術的にいかに優れていたとしてもカッコ悪いのは困るのだ。
●携帯電話型キーボード 2003.4.27
数日前の「ケータイ仕様PC 」を読んでのメールかと思うのですが、こんな情報をいただきました。
ご存知かもしれませんが、世の中進んでいますよ。
◇携帯電話型キーボード◇
http://www.ascii-store.com/shop/directory/00041284.html
貴重な情報ありがとうございます。あるという話は聞いていましたが、実際の商品写真を見たのは初めてでした。
さてこの商品、なにもスペースに問題がないのであればわざわざ使いづらいケータイのキーレイアウトにする必要もないのでは?と、多くの方が思うかもしれない。
しかし考えてみれば現在の世界共通のキーボードのキー配置も、もとはといえばタイプライターの物理的限界よりも速く打たれることを防ぐために、わざと使いづらいであろうキーレイアウトにしたもの。それが今では世界標準。
ケータイのキー配置だってそうならないとも言い切れない。ケータイのほうが早い!という人も少なくないだろう。
●サイトの個性 2003.4.26
サイトにどこまで個性が必要か?最低限の情報を効率的に発信して、それなりにまとまっていて内容が充実していれば、特にそのサイトデザインに個性を強調する必要もないのでないか、とも思われる。
しかしユーザーにとって困るのは同じ業種のサイトがみんな同じようなデザインである場合。わかりやすい例で言えばプロバイダーのサイト。はっきり言って大手プロバイダーのサイトはどこも同じような構成とデザインだ。
困るのはプロバイダーNに行って色々と情報を調べた後、今度はプロバイダーBに行く、またはプロバイダーOに行く、そしてしばらくしてからまたプロバイダーNに行く。たしかこのへんにCGIの情報があったはずだが、あれは確かこのサイト?いやそれともBのサイトか? というふうに記憶が混同してしまい、何度行っても迷うハメになる。
思いきって全面FLASHにするとか、画像無しのテキストだけのサイトマップをトップにするとか、背景を真っ赤にするとか、一度訪れたら忘れないような構成とデザインにしてもいいのではないだろうか。
大きなサイトほど安全=横並びのデザイン、という傾向が強いようだ。
●ケータイ仕様PC 2003.4.25
メールを始めようと思って買ったPCは全く使わず、もっぱらケータイばかりを使っているという人も少なくない。だったら最初っからPC買わなければいいものを…、とも思うのだが。
電車に乗ると7人掛けのシートに座る3人がケータイを突き出して何やらかちゃかちゃと、という光景はいささか滑稽でもあるが、まあ、それだけ普及しているということ。であればいっそのこと使い方がケータイとまったく同じというPCを作ってみてはどうか。BBとかモデムとかOutlookとかは意識しないで本体の後ろにアンテナがついているだけ。契約もケータイと同じ。きっとニーズはあるはずだ。
問題はキーボード。スペースは充分あるのだから、なにもケータイのように1つのキーに重複した操作機能を持たせる必要はないのだからPCと同じでも良い。しかしそうなるとケータイ慣れ人にはかえって使いづらいか?
普段ケータイを使っている人がPCで「い」を打つ時に「A」を2回押す、というのは実際によくあること。
●チャット状態 2003.4.24
ビジネスではチャットまで使うことは少ないようだが、事態が切迫してくると、通常のメールでもメーリングリストでも、ほぼチャットに近い状態になることもある。
これが始まるのは大抵の場合は夜の10〜11時頃、それぞれがパソコンの前に居られる時間帯。そしてこれが時には深夜2時、4時まで続くことがある。
メーリングリストや同報発信の場合は、複数の人が参加するわけであるが、さすがに1時をまわったあたりから、レスが悪くなってくる人がいる。眠いのだ。そして全く音信不通になる人が一人、また一人となり、最後に2人が残る。というのがよくあるパターンのようだ。
そしてこの途中で息絶える人の順序は、ほぼ、年令順、である。もちろん高いほうから。そしてもちろん例外もいる。
●ハマらない 2003.4.23
オタクにとってみれば、多くのパソコンユーザーがその機能を充分に使いこなせず、極めて初歩的なコトも知らないまま使っていることに歯がゆさを感じている。
しかし昔はパソコンと言えばオタクのおもちゃであったが今はそうではない。特にその機能を充分に使っていないからといって勿体無いとか、自分が勉強不足であるとか感じる人は少ない。ハマる必要は無いのだ。
自分のライフスタイルや生活リズムの中で、必要な部分だけを使っていれば満足なのである。メールの受発信ができて、たまにホームページを検索して、DVDを見たり、ゲームで遊ぶ程度でも何も問題はないのだ。あくまでも受け身的な使い方にとどめ、クリエイティブな、突っ込んだ使い方は望んでいない。
その昔、自動車のオーナーは自分でタイヤ交換もできたしブースターケーブルも繋げた。オイルやプラグも自分で取り替えていたし、ラジエーター水やウォッシャー液も自分で補填していた。しかし今ではスペアタイヤも工具もエンジンさえも、自分のクルマのどこにあるのか知らない人も沢山いるのだ。まあ、これと同じようなものではないか。
●コピーの速さ 2003.4.22
CPUの速度が上がり、HDからMOにコピーする時間、またはHDの中にコピーを作る時間がどんどん短くなる。これは良いことなのだが、昔はコピーの間に電話を1本、メールを一通、便所で用足し、と色々なコトができたのだが、どうもそこまでの余裕がなくなってきた。コピーが終わるまでが早すぎるのだ。
また、これは昔からクセというか習慣というか、コピーを作るときに、必ずしも全てのデータが必要なわけではないことがある。そんなときは、予めフォルダから不要なデータを抜いてからコピーを作る。しかし今、改めて考えてみるとそんなことをする必要が全く無いことにも気付く。
昔128MBだったMOは1.3GBに、HDは500MBだったものが80GBに、サーバのディスクスペースも5Mだったものが1Gにと、スペースをケチる必要がなくなっている。同時に不要なものを抜いたところでコピーする時間に大きな影響はない。むしろデータを選り分けている時間のほうがはるかに長い、ということ。
●デジタルデバイド 2003.4.21
商工会議所や商工会が中心となって地域商工業のIT化を推進しよう!なんてことを未だ言っている人がいる。そんなことは無理なのだ。
このようなコトを言っているいる人の多くは地域の商工業者の現実を知らない。IT化を進めるにあたっては、まずはインターネットの環境が必要。その前にパソコンが必要。
朝早く起きて市場に出かけ、帰ってきてすぐに仕込み、日中は厨房で働き、夜は後片付け、という生活サイクルの事業者にいつパソコンをやれというのだ。ワープロも使ったことがなければ、FAXでさえ利用していない事業者はごまんといるのだ。パソコンなどというものには一切関わったこともなければ興味もない人たちなのだ。
こういった人たちに「インターネットを利用しなければ時代に乗り遅れる!」と言ったところで、それはまるで「飛行機が操縦できなければ戦争になったときに生き残れない」と言われているのと同じくらいに実感のないことなのだ。
●知らない言語 2003.4.20
世界的に見れば日本語はマイナーな言語。アフリカや中東で日本語が分かる人は極めて少ない。
アフリカ担当の営業マンが現地で商談をした際に「さよなら、という意味の日本語を教えてくれ」と聞かれ、それは「○○○○って言うんだ」とウソを教えた。もちろん○○○○は放送禁止用語。
その営業マンが帰るときに現地のスタッフが空港まで見送りに来た。そして口々に○○○○!と叫びながら手を降り見送ったそうだ。
さて次に他社の日本人が商談に訪れた。商談自体はうまくいったのだが帰りに○○○○!と連呼されたことに腹をたて喧嘩になり結局は破談。これも営業戦略の一つか。
まあ、知らない言語の単語だけを安易に使うのは、良い結果に繋がらないことが多いようだ。
●ハードの値段 2003.4.19
パソコンが安くなっとはいえ、そのハードのコストパフォーマンスを比較すればケータイには及ばないのではないか。携帯電話という名前ではあるものの、それはもはやPDAを超えたモバイル万能デバイス。動画の撮影と保存、送信が出来てGPSまでついていてメール、電話、時計、電卓と、これ全部ばらばらに買ったらかなりの金額。
バッテリー部分だけでも信じられないくらいのハイコストパフォーマンスである。しかもこれが高くても1万円以下なのだから驚異的。
といっても売っているほうとしては通話料で利益を得るわけなのだから、ハードは赤字でもかまわないのかもしれない。しかしそうは言ってもハードは安過ぎ。10年前に同じ物を作ったとしたら、恐らく100万円出しても足りなかったであろう。
●電話のデザイン 2003.4.18
NTTが電電公社だったころ、国内のほとんどの家庭では510型と呼ばれる、いわゆる黒電話を使っていた。これがNTTの分割民営化によって、色々なデザインの電話器が市場に出回るようになった。
しかしこの当時、電話器、主に受話器には絶対に守らなければいけない寸法の基準があった。それはマイク部分とスピーカー部分の距離と角度。長い時間をかけて人間工学的に練りに練られた究極の寸法であり、これを逸脱すると、とっても使いづらい、電話器とは呼べない代物になてしまう、そう設計者やデザイナーは信じていた。
さらには人間工学的に使い易い重さまで決まっていたのだ。だから今でも公衆電話の受話器はこの寸法や重量を守ってデザインされているはず。確かに使い易いかもしれない。安定性に優れているかもしれない。でも、デカイよなー。。
●更新日 2003.4.17
ウェブページの最終更新日は、そのサイトがどの程度頻繁に更新させているのか確かめる上での目安となる。そしてご存知の通り、この最終更新日だけを定期的に書き換え、その他のコンテンツはそのまんま、などというインチキ表示もある。何を更新したかって?更新日を更新したんだ!などというレベルの低い発想である。
そうかと思えばJavaScriptで自動的に更新日が書き変わる、なんていう仕組みを使っているサイトもたまにあるようだ。まあ、いずれにしても中味が面白くないサイトはいくら更新日だけで誤魔化そうとしても安定したアクセス数を得るには至らない。
さてこれとは逆に1日のうちに何度も更新するようなサイトでは、一体いつの表記にすれば良いのやら…と悩む場合もある。その日の最後の更新作業が翌日にズレ込んでしまったために、翌日の日付けを最終更新日にする。これが正しい表記ではあるのだが、過去のページを検索するときに、内容的に1日ズレてしまうという結果にもなる。
そう突き詰めて考えていくと、そもそも日付けが変わる、という概念が必要ないのでは?とも思うこともある。1月1日の零時を0001として12月31日の零時を8760として、1時間経つと数字が1つずつ増えて行く。途中には日付け、週、月という区切りを入れずにリニアが時が流れていく、というような…飛躍し過ぎとは分かって書いている。。
●保護シート 2003.4.16
新車のシートには汚れ防止用のビニールが貼ってあることがるが、これを永遠に剥がさないで乗っている人がいる。笑ってはいけない。ビデオデッキやオーディオ製品等のウインドウ部分にもキズ防止のための薄いビニールシートが貼ってあり、これに気付かないで何年も使っている人も少なくない。また、事務所や学校の机、特にOAルームのメラミン張りの机上面にもキズ防止の保護シートがぴったりと貼ってあり、その机を捨てるときになって貼ってあることに気付いたりすることも珍しくない。さらにはケータイのLCD画面にも保護シートが貼ってあり、これを剥がさないまま使っているオジサン、オバサンも多いようだ。そして何かの拍子にこのシートに気付き、剥がしてみると液晶画面が思いのほか明るいことに気付いたりもする。しかし笑いごとではない。日本の工業製品はその品質管理を重視するあまり、ユーザー心理を後回しにする傾向があることも確かなようでもある。
●方向音痴 2003.4.15
方向音痴は病気でもなければ遺伝でもない。進んでる東西南北の方角感をきちんと意識してない結果である。常に今どの方角に向かっているのかを意識していれば、そうそうベクトルがズレることはない。例えば今北に向かっているならば、右折すれば東に向かうことになる。これをきちんと意識しないで、街角の目印や風景の記憶に頼ると分からなくなるのだ。
企画やデザインを進める上でも、今は前進しているのか、バックしてレビューしているのか、脇道に入ってオプションを考えているのか、と、こういったプロセス上でのロケーションをしっかりと意識していなければ、いつまで経っても目標に辿り着かないことになる。
方向音痴ではない人でも、夜間、星も月も見えないときに、微妙に円弧を描いたような道を長時間歩けば方向は分からなくなる。また地下鉄の乗り継ぎで何度も曲がったりした場合も同様である。基準となるベクトルを見失わないことが大切でなのだ。
●メカに弱い人 2003.4.14
メカに弱い人の多くは弱いのではなく経験が無いということではないかと思う。オーディオやビデオ機器の配線は、メカに強い人でも簡単にいかない場合も多い。ただしメカに強いという自負があるため最後まで諦めずに作業をするのではないか。
機器の裏側にあるOUTとINの表示というのは、そのジャックがOUTである場合と、そのジャックにOUTのプラグを差しなさい、という意味の場合とがあり、これはメカに強いとか弱いとかに関係なく難しいのである。やってみてダメだったら差し直す、または取り説を何度も読み直してチェックする、のいずれかの作業が必要となる。もちろん最初に差したのが正解で、簡単に作業が終わってしまう場合もあるが。
また、メカに弱いからパソコンはよく分からないと言っている人の多くは、パソコンを勉強したくない理由として自分がメカに弱いということにしている場合がほとんどであるようだ。
●メール処理 2003.4.13
WEBに絡んだ仕事を長年やっているとおのずと1日に処理しなければいけないメールの量も増えてくる。ところがこれが増え過ぎてしまい、全てを読んで必要なものを選んで返信するという作業で半日かかってしまう場合もある。
仕事のメールは1通でもおろそかにはできないのできっちり読む。その代わり無用な広告メールや忘れたころに配信されてきたメルマガ、スパムやウイルス、フォームから送信された発信者のメルアドがないものは、タイトルだけを見て片っ端から捨てていく。
まずは必要なものとそうでないものを振り分けなければならない。それでもまだまだ返信が必要であろうメールが残っていることもある。さてそこでどうしたらいいか?と考えてみると「レスするべきか否か」で迷っている時間が意外に長いことに気付く。であれば全てにレスする!と決めて、片っ端からレスしていくという方が早いようだ。
ただし勢い余って勇み足的失言、ということもしばしば。。
●ノーチェック 2003.4.12
内容は一昨日の続き。メールでなぜ失言が多いか?もう一つの理由が、書くと同時に読んではいないということ。なんのこっちゃ?と思われるかもしれないが、会話や電話では実は喋ると同時に自分の耳で自分の言ったことをリアルタイムで確認しているのである。
メール、に限らず「書く」という行為ではこれができない。今まで、少なくともワープロやメールがない時代に紙に文字を書いていたときには、ほとんどの場合、自分が書いたものを自ら読み直して確認し、訂正していたはず。これがケータイのメールやチャットなどでは自分で確認しないまま相手に送信されるということになってきたわけだ。だからこれが聞き手の存在しない言葉と同様、思い付くまま、自己中心的な情報として相手に流れてしまうということになる。これは実は非常に危険。相手も、自らもノーチェックの情報は、思い込みや潜在意識がモロに反映されてしまうのである。
アブナイ発言を掲示板にカキコする人の多くは、実際に会ってみると非常に大人しい穏やかな性格であったりもする。
●カンバン 2003.4.11
大手企業の第一戦で活躍していた営業マンがその企業を退職して個人で商売を始めた。ところがこれがなかなか思うようにいかず、2〜3年後にもといた大手企業に舞い戻って来るというケースがある。
いくら実績と実力がある営業マンでもその企業のカンバンである「ブランド」を外されてしまうと、今まで通りにはいかなくなってしまうことが多々あるらしい。最初のうちは、もといた企業の関連会社に行けば、付き合いでそれなりの仕事をもらえる場合もあるし、その企業名を出すことで、多少は優先的に取りはからってもらえる場合もある。しかしこれらはいずれも長続きはしない。
「私は元○○○○にいました」と、何年経っても言い続けている人もいるが、こういった人の多くはあまり成功しているとは言えないようだ。
日本では一部上場企業がGDPの大半を占めている。そしてその就労率は全就労人口の数%。いくら「大手といえども安心できない」と言っても、そのカンバンの持つ影響力と魔力はまだまだ巨大であるようだ。
●インターラクティブ 2003.4.10
メールでは、自分の考えを文章でまとめてから送信する、客観的な見直しができる、証拠が残る等々、電話に比べるとそのメリットは大きい。
しかし主にプライベートメールや掲示板への書き込みでは、兎角些細な勘違いや失言が元でトラブルになることが多い。その原因は、まずはチャットは別にしてインターラクティブでは実はないということ。対面での会話や電話では、失言、または相手を不愉快にさせるような発言、これらに気付くのは多くの場合、相手の反応である。相手の表情や口調、雰囲気が変わったことで「あ、まずかった!」と気が付くのであり、気が付いたからには焦ってフォローしたり、発言を取り消したり、素直に謝罪したりすることができる。
しかしメールや掲示板への書き込みでは、相手が反応するのは全て書き終えた後ということになる。失言を含んだまま途中で訂正されることなく発信されてしまうのである。
だからメールを書く時には、会話以上に読む人間の立場になって見直す必要があるようだ。
●通訳 2003.4.9
デザイナーの仕事の中に通訳というのがある。といっても外国語⇔日本語ではない。デザイナーは外国語が苦手なのだ。では何の通訳かというと技術者⇔営業。この両者、場合によっては全くお互いの言語が通じない場合がある。
WEBで言えばSE⇔営業、というケースが多い。サーバにアクセスが集中したときに少しでも負荷を避けるために、できるだけ画像は使わず、テキストだけで処理できないか、というのがSEの意見。しかしカメラマンが苦労して撮影してきた写真を、なるべく大きくきれいに載せたい。またスポンサーのバナーは出来るだけ派手に目立つように見せたい、というのが営業の意見。
この両者の意見をまともに聞いていたのではデザイナーは仕事にならないという現実もあり、SEに対しては、なぜ写真が大きくある必要があるのか、一般的なユーザーはどういった価値観を持っているのか、等々を理論的に説明しなければならない。一方営業に対しては、サーバに負荷がかかるとどういうコトになるのか、単純に他のサイトと比較できない諸々の条件があるコト、等々を噛み砕いて説明しなければならないのだ。
と、このような仕事が増えてしまったために、この通訳業務がルーティンの仕事になってしまい、デザインという作業を全くやるヒマがなくなってたデザイナーというのも実際にはいるらしい。
●やはり使えぬNN7 2003.4.8
Netscape7のシェアが少しずつ伸びているのではないかというコトを以前書き、実際にも1ヶ月ほど使用してみたが、やはりいくつか使いにくい問題がありメインでの使用は止めた。とりあえずは表示確認用としてのみにしようと思う。
まずはISO-2022-JPという文字コード。こいつが特にメールで使うには実に始末が悪い。日本語の記号の中にも使用できないものがあり、メール本文の一部が化けてしまい、相手に真意が伝わらない場合がある。
次にブラウザ画面上での画像の保存が今までのようにドラッグ&ドロップではアーカイブでの保存になってしまい、画像だけを保存するためにはプルダウンを使用しなければならない。WEBデザイナンでは頻繁に行う作業なので効率が悪い。
もう一つがメールでの返信の際に、アドレス帳からメルアドをドラッグ&ドロップすると宛先にしたくても強制的にCCやBCCになってしまうということ。一般的に返信の際には宛先を変更することは無いのだが、アドレス帳からドラッグ&ドロップすることで名前と敬称が入るという(本文の最初に相手の名前を書かなくてもいいように)方法をとっているので、これをいちいち変更するのは実に面倒。
それでもちょっと勿体無いと思ったのはパスワードマネージャー機能。これは便利ではあったが…いずれにしても、あとはSafari待ちといったところか。
●犬小屋-2 2003.4.7
これで万全と思いきや、木ネジではアタマが潰れてしまってうまくいかず、簡易作業台はことのはか安定性が悪く使いづらい。単板は合わせ目の寸法がきちんと出ずスキ間が空いてしまう。
というようなことで、いつまで経っても犬小屋が完成しない。と、こういうコトをいつまでもやっている人がいる。最初の段階で揃えた環境を正として、何とか最後まで作り上げようと意を決すればいいだけのはなしなのだ。それでも完成しないとするならば設計図がきちんと出来てないうちにスタートしたからだ。
モノを作る時、プロジェクトを進行させる時、確かに途中でレビューすることも大切であるが、レビューばかりしていて問題を発見しては後戻り&リセットしていてはいつまで経っても完成しない。
トンカチやノコギリは人材、板はコンセプト、と例えると分かりやすいだろう。まあコンセプトを変更するのは自由であるが、人材がすぐに取り替えらられるのではたまったもんじゃない。道具とはいえ人間である。
●犬小屋 2003.4.6
犬小屋を作るためにトンカチとノコギリと板を買ってきたのだがうまく作れない。まずはトンカチ。頭の片方が釘抜きになっているタイプにしよう。ノコギリは犬小屋を作るためには大きすぎたようなのでもっとコンパクトなものにしよう。板は厚すぎたために切るのに時間がかかりすぎる。というわけでこれらの道具と材料を改めて買いに行く。
ところがまだうまく作れない。釘抜きは別に専用の釘抜きにしたほうが効率的のようだ。ノコギリはやはり時間と労力を省く為に電動式にしよう。板は薄いと切るのは楽だが反ったり曲がったりしてしまうので合板にしたほうが良さそうだ。ということでまた買いに行く。
ところがどうもうまくいかない。釘抜きを使う以前に釘では打ち直しが厄介なので木ネジを使ったほうが確実なようだ。電動ノコギリを使うためには簡易式の作業台があったほうが良さそうだ。合板を使うと犬がシックハウス症候群になるかもしれなのでやはり単板できちんと加工したほうが良いだろう。というわけで再びホームセンターへ。…続く
●デザイナーの真価 2003.4.5
技術者が製品を作ったときには、そのスペックを表示することができる。スペックだけではなく時にはコストや開発期間を数値化して社内やクライアントにプレゼンテーションすることが可能であり、その数値というものが実に強い説得力を持つ。
営業の場合も売上げ、利益、という数値化できる武器を持っていて、これも絶対的な訴求力を持っている。プランナーにしても色々と数字を駆使して説得力のあるプレゼンテーションが可能である。
しかしこういった数値化できるツールを持っていないのがデザイナーである。まあ、稀にコストダウンや省力化をコンセプトとしたデザインを提案することもあるが、それがいかに優れたコンセプトであっても売れなければ仕方がないし、カッコ悪ければもともこもない。
というわけでデザイナーでもプレゼンテーションの際に色々とマーケティグの結果や未来予測を織りまぜた手法が流行った時期があったが、これはどちらかというとプランナーの範疇でもあり、極端に言えばかっこいいデザインを作り上げる能力の無いデザイナーなこういったことを進んでやっていたとも言える。
やはり何といっても見た瞬間に「お、かっこいい」「わーキレイ!」と思わせることがデザイナーの真骨頂である。
●夢物語り 2003.4.4
情報が断片的な場合、人間つくづく自分に都合の良い方向に考えるものだ。ホームページを作ろうと考えている人で、作ること=簡単=素人でもすぐに出来る、という発想の人が実に多い。しかも自分で作る場合は自分でその構成やデザインも考えなければいけないはずなのに、考えなくてもかっこいいサイトが出来ると勝手に思い込んでいる。
また、プロに頼む場合でも1万円も出せば立派なサイトをすぐに作ってもらえると思っている人も多い。まあ、1万円は極端にしても、お金さえ出せば勝手に作ってもらえると勘違いしている。自分のサイトのコンセプトや方針、必要な写真やその他諸々の資料も何も用意しなくてもだ。
仮にそれでも何とかホームページが出来たとすると、今度は黙っていても世界中から沢山の人が見に来てくれて、ホームページで何か商品を売れば、放っておいてもどんどん売れるものだと。
こういった夢物語りと現実とのギャップを噛み砕いて納得してもらうまで説明するところからWEBデザイナーの仕事はスタートする。
●サーバをアーカイブに 2003.4.3
アーカイブというのは直訳すれば書庫、つまり過去のデータを保存してためておくところ。ホームページのデータは場合によっては毎日のように更新するのであるが、これをサーバにためていくといずれはデータで一杯になってパンクする(実際のタイヤのように爆発するわけではないが)。
インターネットが普及し始めて5年も経てば、それほど更新頻度が高くなくてもそろそろ一杯になるころ。昔作って今は使っていない画像データが書庫の中に堆積しているサーバも多いことだろう。また、過去の記事を検索するようなシステムを利用しているとすれば、それなりにきちんとした形でデータが貯まっているはず。
さてここで問題は、果たしてサーバをアーカイブとして利用することにどれくらいのメリットがあるのだろうかということ。CDにでも焼いてバックアップしておき、サーバのデータは更新するたびに過去のものに上書きしていってもいいのではないか。たしかに過去の記事を検索したりリンクできたりすることもメリットではあるが、果たしてそこにどれだけのアクセスがあるのか?たいした数でなければ 思いきって捨ててしまおう。サーバの残り容量を気にしていたのでは、動画なんかおっかなくて載せられない。
●MSの戦略 2003.4.2
.NETとかいう難しい話ではない。メールの添付ファイルにWordで作った種類がくっついてきてこれを開くと何ということはない、ただテキストが打ってあるだけ、なんてことがよくある。何でメール本文に書かないのだろうか?と思うのだが、まずはwordの文章をコピーしてメールに貼付けられるということを知らない人が多いのである。
そしてもう一つ、文字(テキスト)はWordで打つものだと思っている人が多いのである。そしてそういった人にWordの全文を選択、コピー、そしてOutlookに貼付けを実際にやって見せると「おー!」と感心されてしまう。ついでにCtrl+v、又は右クリックを使うとさらに「うぉー!」と感心される。
そしてアクセサリーの中からメモ帳を開いてそこに文字を打ってみせると、「えー、そんなのがあるんだー!」。さらにワードパッドを出してみせると「えー知らなかった!」といった具合。決して初心者ではない。日常的にパソコンを使っている人たちである。
まあ、それにしてもよくぞここまでワープロ=Wordという概念を広く植え付けたものだと感心させられるマイクロソフトの戦略である。
●光学式マウス 2003.4.1
玉コロのついてないマウスを使っている人が多くなってきたが、中にはどうも使いづらいと言う人もいる。思うように動かないらしい。「おっかしいなー?」と言いながら、マウスの裏側を、そのマウスが♂か♀かを見分けるのに苦慮しているような目つきで睨んでいたりする。
一般的に玉コロがついているマウスは動きが悪くなれば玉をはずしてローラーを掃除したりマウスパッドの表面をきれいに拭いたりすればその動きは改善されるのだが、光学式の場合は気休めにも掃除するような部分が無い。
自動車の故障はどこかを叩いたり蹴ったりすれば稀に治ることもあるがパソコンの場合は叩いて治るケースはほとんど無い。とはいえ何かが壊れたときは掃除してみたり叩いてみたりしたくなるのが心情でもある。
さて光学式マウスの動きが悪い場合の原因であるが、その多くはマウスパッドが部分的に「青い」ためである。
過去記事
.