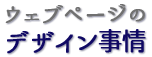2007年2月
教科書は勉強をするための参考資料である。もちろん教科書をより深く理解することが受験に対しては有効ではあるが、世の中には教科書に載っていりことよりも載っていないことのほうが遥かに多いのだ。 といったことは誰しも理解しているつもりでいるのだろうが、実際にウェブサイトを作るときには、いわゆる教科書的書籍に書いてあることを鵜呑みにして、その通り作ってしまうというケースも少なくないようだ。特に「売れるネットショップ」というようなタイトルの書籍は、そこに書いてある通りに作ったとしても実際に売れる可能性は極めて低い。そこに書いてある内容を理解した上で、自分の考えや経験を照らし合わせ、独自のコンセプトを構築しなければいけないのだ。教科書通りに作ったのになぜ売れない?なんて思っているようではダメなのだ。
インターネットであろうがアナログであろうが、消費者の中で、その商品やサービスを必要としている 人の数は限られている。マニアックなもの、特殊な用途に限られたものは無尽蔵に売れるということはない。 必ずどこかで頭打ちになる。
ということで、これを打開するためには、その用途やニーズをも開拓しなければならないのだ。 ところが他人が苦労して開拓した市場に割り込んできて、価格破壊をして、自らも利益を 上げることなく、その市場を荒らすだけ荒らして去って行く者もいる。
価格破壊と呼ばれようがビジネスとして成功すれば、それは勝ち組と呼ばれ、失敗すれば 犯罪者扱いだ。紙一重のところでもあろう。
今では多くの企業や事業所がウェブサイトを公開している。個人商店や個人事業主の多くもウェブサイトを 持っている。そんな状況の中で、ホームページを持っていないと、これからの商売は成り立たない!などと 思われがちであり、すでにここ8年間は、そのようなことが巷で囁かれ続けている。
でも現実はどうだろうか。全くITにもパソコンにも関係ないところで、今まで通りにきちんと商売を している人もたっくさんいるのだ。むしろそういった人たちの割合のほうがはるかに多いだろう。 「インターネットなんて無くても行きていける。」というのは都市伝説ではない。
その一つが2004年ごろから各検索サイトで始まったパーソナライズ検索で、ユーザー一人一人の趣味嗜好や過去の行動、購買情報に基づくアルゴリズム。既に検索のパーソナライズ化は着実に進展しているようである。
このことで検索結果が人によって変化するということになり、キーワード毎のランキングで一喜一憂する行為が過去のものになるというわけだ。ただし従来のジェネリックな検索結果も残るわけで、全てがパーソナライズ検索に移行するということではない。しかし今までのページランキングがもつ影響度は大きく低下しつつある。
いずれにしても今までのようにGoogleやYahoo! Japanで何位になった!なんて自慢している時代は終息しつつあるようだ。
そもそも検索エンジンはスパムとの戦いで、当初のinfoseekやexcite、Altavistaなどでは、ほとんどの キーワードでアダルトやUG系サイトが上位に来るという悲惨な状況が続き、こういった不正SEO対策とのイタチごっこを繰り返して いるうちに、98年、Googleが画期的なアルゴリズムを引っさげて登場し、今では検索エンジンのシェアを席巻したということだ。
しかし現在検索対象ページが膨大になり過ぎ(確か昨年ぐらいまではGoogleのトップページに検索対象ページ数が表示されていたはずだが、いつのまにか消えている。最後に見たときは33億ぐらいだったと記憶する。現在は400億とかいうことだが)、ユーザーが本当に必要とする情報がすくいあげられなくなり、ここをどう解決するかがテーマになってきているようだ。検索エンジンも明らかに次のフェーズに入ってきている。
郵便振替は今でもこの方法で販売しているところもある。 「郵便振替用紙」には「払わなければいけない!」という無言の プレッシャーがあるのと、地方では近くに都市銀行がないので、 これがけっこう有効だったりもするようだ。
別途連絡は施行された内容次第で許されるかどうか? という問題もあるが、 逃げ手としては「有り」になるかもしれない。
また、こういったサービス↓もあり、
http://www.netprotections.com/atobarai/
経済産業省の動向によっては、これと似たような サービスも色々と現れてくるかとも想像する。 いずれにしてももうちょっと様子を見たほうが良さそうだ。
決済方法に代引きを追加するというのは一般的な対応ではあるが、その他にも
・銀行振込だけでも前払い、後払いを選択できるようにする
・銀行振込で全て後払いとする
・後払いは郵便振替とし、郵便振替用紙を同封する
・後払いご希望の方はその旨別途連絡させる
などが考えられる。
銀行振込で全て後払いは、 2000年以前のウェブショップはこの方法が多かったわけで、 まだインターネットが浸透していなかったため、売るほうがリスクを負う というもの。実際に不払いで催促しなければいけないケースも 稀にはあり、悪意というより忘れてる、ついつい後回しになって しまう、という感じのものが大半ではあったが。
例えば広告メールに「未承諾広告」と書くことが数年前に義務付けられ、 当初はほとんどの広告メールのSubjectに「未承諾広告」と入っていたが、 「未承諾広告」というSubjectを見た途端に読まずに捨てられていますという 現実もあり、徐々に「未承諾広告」を入れた広告メールは減り、今では皆無だ。
一方、消費税の税込み価格表示は、今でもほとんどのサイトで守られている。まあ、これは実店舗での販売でも義務付けられていることでもある。
いずれにしても施行されるまでは、紆余曲折あるのではないかと思われる。
経済産業省では、3月から検討に入り2009の施行を目指しているようだ。これは代引きを義務付けるというふうにとられがちだが、実際には、商品の後払いと先払いを消費者が選択できるようにするというもので、先払いを悪用した詐欺を防ぐためとされている。しかし
・物販以外のサービス(商品受渡しが発生しないもの等)をどうするか
・後払いを悪用した消費者側による詐欺行為をどう防ぐか
・この義務に従っていない場合はどのようなペナルティーをどうやって与えるのか
等の課題もあるだろう。
意外なことにウェブサイトの営業はこのご用聞きが効果的だ。特に更新業務については、電話でのご用聞きをしてみると、 けっこうな確率で「あ、そうそう、そろそろお願いしようと思ってたんですよ。」というレスがもらえる。 逆に言えば、それだけそのクライアントの中でのウェブに対するプライオリティーは低いとも言える。 現実は実店舗や従来通りでのアナログチックな商売のほうがはるかに重要であり、売上げに占める 割合が大きいということであり、どうしてもウェブは後回しにされがちなのでもある。
またFLASHファイル内で文字を追加すれば、そこそこ鮮明で ファイルの重さにもほとんど影響しないのだが、 読込んだムービーファイルは作業中に音声を再生できないので 同期が非常に難しい。 音声だけ別ファイルにすればFLASH上で音声を再生しながらの作業も 可能ではるが、元データから音声トラックだけを書き出さなければ いけないので、これもけっこうな手間。
それと画質的に文字が馴染まないという問題もあり。結論としては「思いのほか難しい」 ということだ。
という要望も多いのだが、 日本のテレビではNTSCという規格で走査線の数は525本。 仮に動画の縦方向のサイズが240pixとすれば、単純にドッド数で換算すると 通常のテレビの2倍の大きさにしないと認識できないということになる。 さらに画面自体が小さいので、その分も考慮しないといけない。 また、文字を認識できる解像度に映像全体を設定しないといけないので、 このためにファイル自体が重くなってしまうのだ。 このへんをどこで妥協するか、ということを考えるのにえらく時間がかかるものだ。
その手順は、 まず元データ(DVテープから書き出した.movや.avi)をQTproとかiMovieで大雑把 (狙いよりもやや高品位)に圧縮(コマ数、圧縮方式、音質など)する。 次にFLASHに読込み、ここで詳細な品位 (キーフレーム数、想定回線速度、画質など)を設定する。 そしてFLASHからストリーミング用.flvファイルを出力。 最後にFLASHからパブリッシングで.swfファイルを書き出し。 という感じで、それぞれに設定があり、その選択肢もたっくさん 有り過ぎてよくわからん。
QRコードの使い方を知らない人は多い。実は使い方が分からないのではなくQRコード自体を知らない ということらしいのだ。高校生や大学生でも「わからな〜い」という学生も少なくない。
ではなぜこれだけ便利なものが以外にも普及していないかというと、 その要因の一つが「QRコード」という呼び名ではないのだろうか。 高校の情報の教科書では「二次元バーコード」と書かれていて、恐らく NHKで放送される場合もそう呼ばれるだろう。
「QRコード」はデンソーの登録商標で、ケータイ各社でも機能の 名称として「バーコードリーダー」となっているものが多いようだ。 つまり名称が定着していない、ということのようだ。
「バリアフリー」「ユニバーサルデザイン」「アクセサビリティ」などという 言葉は聞こえが良いので、これらを金儲けのネタに利用しようと考えている人間も多い。
しかし何百万もかけて市町村のサイトを「バリアフリー」「ユニバーサルデザイン」「アクセサビリティー」 対応する予算があるならば、車椅子の通れる歩道を拡張したほうがより現実的。 そして全盲者には全盲者専用のサイトを別途立ち上げるべきだだろう。
健眼者と全盲者が兼用できるサイトというのは現実的にはかなりの無理がある。 自転車と車椅子を合体させた乗り物を作るようなものではないかと思うのだが。
そもそも全盲者や重度の視覚障害者にとってはビジュアルデザインは不用なので、全く異なった切り口から サイト構成を考えていかなければならないはず。
その前に、まずは視覚障害者がどの程度アクセスしてくるのか?その障害の種類と度合いは? というようなことを調べてからでないと適切な対応はできないだろう。
単にその画像が何を意味しているのか分かるようにaltタグを入れるだけでも、一つ一つの画像の 説明文(視覚障害者が音声で聞いて分かるような)を考えるにはそれなりの手間がかかるわけだが、 アクセスする視覚障害者の障害の度合いによっては、聴覚障害を伴っていたり、長時間の音声認識が 不可能であったり、知的障害を伴っていたりする場合もある。
そうなると、ほぼOneToOneに近いデザインが必要にもなってくるわけだ。
また、全盲以外の視覚障害者にとっても、文字は小さすぎ、色の使い方も視覚障害者を意識しているとは言えないものも多い。 利用者側でテキストサイズを利用者側で可変でき、特にリンクする文字は大きく目立たせるといった、根本的なユニバーサル デザインにさえ対応してないサイトも少なくない。
それらのサイトは、形式上、又は対外的に「アクセシビリティに対応した」というもので、 実際の使い勝手はほとんど考えていないようだ。
というわけで、対外的に「アクセシビリティに対応した」と言えるものを作るのは簡単だが、 本当に視覚障害者にとって「優しく」するのは 非常に大変ということ。
また、全盲者ではなく、視覚障害者全般をターゲットとした場合には、近眼、老眼、弱視、色盲、などなど様々なケースがあり、そのレベルも個人差が大きく、視覚障害者全体に対応するのは現実的には不可能。
仮に視覚障害者全体ではなく、できるだけ多くの視覚障害者に最大公約数的に 対応するのであれば、画像データを極力使用せず、テキストだけの極めてシンプルな構成にするということになる。
しかしアクサシビリティへの対応を推奨するような内容のサイトであっても altタグにすら対応していなかったり、ソースを見る限り決してアクセシビリティに対応してるとは言い難いというものも多い。 音声読み上げソフトで読み上げても、恐らく全盲者には理解し難いページも多々ある。
基本的にアクセシビリティは全盲者に対する対応となり、そのためには音声認識ソフトで読み上げ可能な対応が必要となる。 また、単に読み上げるだけでなく、その内容が全盲の人でも理解できることが前提となるはずだ。
実際には日本の全盲者の数は20万人、人口比では0.002%以下。さらに全盲者の中で音声認識ソフトを使用してウェブにアクセスする 人の割合は、恐らくその半分以下だろう。
今では多くのサイトがFLASHを使用しているが、FLASHのアクセシビリティ機能はIEでのオンマウスでそのテキストは確認できず、 音声読み上げ時にのみ対応する。ということは読み上げソフトが無いとその効果が検証できない。
そこまでやっているサイトは極めて少ないのではないか。
現実問題として、アクセシビリティに対応するためには全ての画像ファイルにaltタグを追加しなければならない。 これは制作する上では相当な時間を要し、それなりのコストがかかる。
しかし健眼者にとっては全くその変化はわからないというもので、アクセシビリティに対応しても、健眼者にとっては、 単にコストアップになってしまったという結果にしかならないので特別なサイト(公的役割が高いサイト、確実に視覚障害者がアクセス するであろうサイト)以外には対応していないのが普通であろう。
ウェブを作る上で難易度の高い作業をする場合がある。FLASHで高度なActionScriptを書いたり、3Dソフトでデータを制作して動画に変換したり、Illustratorで元になる画像を制作したりと、そんなときだ。
しかし、高度なアプリケーションになればなるほど、理論を理解しないまま何となく成り行きで成果物が完成してしまう場合がある。そしてしばらくして同じ作業をしようとしたとき、また一から思い出して、またはマニュアルを読んだりしながら進めることになる。もったいない話だ。
とはいえ思ったものが出来てしまえばそれで納期が守れる。であれば、なかなかそれ以上のことはやってるヒマもないというのも事実。人間の脳みそとは実に揮発性の高いメモリーである。
失敗しているウェブサイトの多くは、クライアントに言われた通りにウェブ制作者が作ったものだろう。クライアントがマーケティングやプランニングの専門家であれば別だが、多くの場合、クライアントが提示してくるコンテンツや構成のアイディアは、そのまま作っても成功するものではない。
全く旧態依然とした無個性なものであったり、人的費用がケアができないにもかかわらず極端に高いレベルのものであったり、商品数が30個しかないのにアマゾンと同じことをやろうとしていたり、Yahoo! Japanの検索結果でトップになることだけを夢見てコンテンツはほとんど考えていなかったりと、まあ、色々とあるのだが、いずれにしてもクライアントはウェブの専門家ではないのだから仕方がない。
ここで勇気をもってクライアントのアイディアを否定し、その条件に見合った適切なコンセプトを提示する。と、まずはここから始めなければいけない。言われた通りに作るなら誰でもできるし、成功しないサイトを作ってしまうと次の仕事は来ない。
プロジェクトの中で与えられた一部の仕事をする時、そのプロジェクト全体が見えている場合と、自分の与えられた部分しか見えてないとでは大きな違いがある。全体が見えていないと自分の仕事の成果の可否も判断できずに、心配になり、余計なことまでやらかしたり、主旨とは違う方向のことをやらかしたりするわけだ。
それでダメ出しを喰らったあとに「言われた通りにやったのに。。」と愚痴ることとなる。ここが下請けで終わるかプロデューサーになれるかの違いでもある。下請けは常に愚痴を言っていなければならない運命なのだ。
スクロールがどうしても長くなるのであれば、フレームで切っていつでも他のページに移動できるようにする。それができないのならば、せいぜいスクロールの量は、XGAの縦方向の2倍以内に収めるのが適当であろう。
とにかくページごとにスクロール量がバラついているのは見づらいものである。仮にページの長さがまちまちの本があったとすれば、そりゃあ読みづらいことこの上ないし、TVの画面で表示されるテキストを視聴者側にスクロールさせたりすれば、この上ない不親切な行為である。 また銀行や図書館の端末画面でスクロールが必要となれば、その使いづらさに苦情が殺到するだろう。
スクロール無しで、ぱっぱと画面が切り替わる、そういった画面がいかに使いやすいものか、今一度考えてみるべきであろう。
巻物のように長〜い長〜いスクロールのページに行き当たることがある。ブログやニュース系サイトならそれでもOKだ。日記やニュースは新鮮さが勝負であり、言ってみれば新聞のようなもの。
しかし仮に新聞紙に長編小説や画集、百科事典が印刷されていたらどうだろう。読みにくいこと、検索しづらいことこの上ないだろう。それと同じで、多くのコンテンツを多岐に渡って掲載しているサイトで、1ページごとに長々とスクロールを強要されるサイトは見るのに疲れる。しかもスクロールして一番下まで行ったら、また上に戻らないと他のページには行かれない、なんていうのもあるもんだ。
コンピュータではスクロールが当たり前のように思われているが、ほどほどにしておいたほうが良かろう。
.