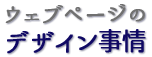2007年11月
時代的にはプレゼンは3〜5分という短い時間内で、どれだけ内容の濃いものを効率的に訴求できるか?ということが評価の基準になっている。 昔はいかに長時間喋り続けて、いかに多くの資料を作るか、という部分も評価の対象になっていたが、これはここ10年ぐらいで明らかに違ってきているようだ。 もちろんペラ1でも内容が希薄なら意味はないし、分厚くても内容がそれ以上に圧巻であれば良いのだが。
バブルの頃には、けっこう分厚い資料が来ても、それに目を通している時間があったし、そういう業務を専門に しているスタッフもいたものだ。もちろん今でも役所なんかはそれが本職なのでじっくり目を通すだろう。
ただし民間ではそういう時間もスタッフも削減されてきていると同時に、ウェブや他のデータの引用で、分厚い資料は 誰でも比較的簡単に作れるようになった。 とはいえ上司や社内に提出するときに量の多さがモノを言うというケースは今でもあるのだろうが。
プレゼン資料はいかに完結にシンプルにコンパクトにまとめるかが肝要。配布された資料をパラパラとめくって「こんなにあるのかぁ。。」と感じさせない範囲が良いだろう。 配布される側の立場で考えると、どんなに素晴らしい内容でも15ページ以上になると読むのが 労働に感じるものだ。 やろうとしていることを全部書くのではなく、目的やメリットをできるだけ短い時間で相手に理解してもらい、納得してもらうような作り方が良いだろう。
であれば、そんなところからホームページの制作依頼は請けないほうがいいだろう!ということにもなる。しかし逆にきちんとコンセプトも固まって、コンテンツも仕様も原稿も全て揃ってから制作するなんていう状況は滅多にあるものではない。ある程度(この「程度」には大きなバラツキがあるのだが)は見切り発車できる体制がないと、ウェブ制作の仕事も請けられないだろう。クライアントからの完璧な資料の提示を待っていては、恒久的に待たされることになる。
特に資金繰りが苦しくなってきた場合や、今までの取引先から切られてしまって受注が激減して焦っているような場合は、経営方針が決まらないうちに、すぐにカネになりそうな処を次から次に当たって、ちょっとでも感触が良ければすぐにその内容をホームページに反映しようとするのだ。
今のご時世、そうそう簡単に新しいビジネスが展開できるわけは無いし、焦って情報が不足しているままスタートしたところでロクな結果にはならんのだが。
しかし、何をやりたいか自分で分かっていないから、それを模索するべく営業活動のためにホームページが必要らしい。となると営業先を1件訪問するたびに「やりたいこと」の内容も変わってくる。それぞれに色々な可能性があるように思えてくるので、その訪問先から帰ってくると修正依頼が来るということになる。そもそも自分でやりたいことの骨子というか根本的な部分が決まっていない段階で、色々と訪問するからいけないのだが。
![[ウェブページのデザイン事情・画像]](http://www.swany.ne.jp/minba/u/ni/moodykatsuyama.jpg) |
「急いでホームページを作ってくれ!」と言われることがよくある。コンセプトもコンテンツも決まっていない状況では出来るわけないのだが「任せる!」と言われて、その場で出来る限りの情報を集めて何とか見繕う。しかし作っている途中で「あれも入れてくれ。これも必要だ。」という感じで色々と五月雨式エンドレスの修正依頼が来る。結局は自分でやりたいことが分かっていない段階でホームページ制作を依頼すること自体が間違いなのである。
応用問題が苦手な理由としてケータイの利用があるのではないかとも想像する。ケータイサイトをデザインすると分かるのだが、たかだか4cm x 5cm程度の画面の中に必要な情報を効率的に詰め込むのは簡単ではない。また、階層構造もちょっと複雑にしただけで極端に使いづらいものになる。
つまりケータイは必要最低限の情報を効率的にシンプルに吐き出すための窓口なわけだ。こういった情報を毎日閲覧しているうちに、応用問題のような紛らわしい情報と出会う機会は少なくなり、そもそも応用問題を解くということ自体が日々の生活の中で必要なくなってきているのではないか? などとも想像するのだが、どうなのだろうか。
最近の子どもは応用問題が解けなくなっているらしい。しかしこれは決して頭が悪くなったとかIQが下がったということではないだろう。原因は時間の流れの早さに対応するためではないかと思われる。大量の情報を手際よくタイムリーに処理していくためには、目前の情報を瞬時に理解し即決しなければならない。1つの事柄を熟慮している時間が無いのだ。このことは子ども同士の会話でトピックの移り変わりの早さを観察すれば分かる。
応用問題は苦手だとしても、複数の教科の単純な問題をランダムに大量に処理していく能力は高いんじゃないかと想像するのだが、どうなのだろうか?
![[ウェブページのデザイン事情・画像]](http://www.swany.ne.jp/minba/u/ni/nisikawaayako.jpg) |
クライアントから断片的な情報が五月雨式に来る!というのはよくあることだ。ちゃんとまとめて一度に出してくれや!と言いたいところである。しかしクライアント側としては、気がついた時に出してしまった方が気分も楽だし、情報をまとめるという厄介な作業も省略できるというもの。
従って五月雨式情報に対して、毎度クレームをつけていたのではクライアント側も「うるせえなぁ」という気分にもなるというもの。しかし放っておいていつまでも五月雨ではこちらもたまったもんではない。 どこまで我慢するのか?が、クライアントとの健全な関係を維持する上でもポイントとなる。
![[ウェブページのデザイン事情・画像]](http://www.swany.ne.jp/minba/u/ni/takesitayosie.jpg) |
しかし非営利目的の事業でも問題は多い。カネが絡まないだけに、評価や結果の基準になるものが無いというのもその一つ。結局は一番苦労した人間がまったく評価されずに、大した働きもしないが要領よく立ち回った人間が評価されるというようなことだ。
そして最も大きな問題は、批判的な人間、役に立たない人間、かき回すだけで周りに迷惑ばかりかける人間をそのプロジェクトから外すということが極めて難しいということだ。営利目的であれば、ばっさりと切れるのだが。。
![[ウェブページのデザイン事情・画像]](http://www.swany.ne.jp/minba/u/ni/nisiokasumiko.jpg) |
営利目的ではなく、地域での有志やボランティアによるインターネットを利用した事業というものがある。こういった事業ではカネが絡まないために、比較的クリーンで爽やかに事業が進行するケースも多い。
ウェブ制作にしても、そこに関係する開発や営業活動でも、カネの匂いがしなくなった途端にさっと身を引いていく業者も多く、そういった業者が関わらないことで、よりスムーズに事業が進むということにもなる。
![[ウェブページのデザイン事情・画像]](http://www.swany.ne.jp/minba/u/ni/kozimayosio.jpg) |
デザイナの間では使い古された言葉であるが、これはウェブデザインにおいてもモロに当てはまる言葉でもある。フル装備の至れり尽くせりのサイトを作ったところで実際にアクセスが集中するのは階層の浅い数ページのみ。時間をかけて丹念に調べて作った階層の深いページはほとんど誰も見ていないというのが実情のようだ。
こういった現象が理解されつつあるためだろうか、最近では既存のサイトをシェイプアップしたシンプルなものにリニューアルしたいという要望も増えてきている。
まあ、制作側としてはページ数が多いほうが費用が高くなるので、あまり喜ばしい現象ではないのだが、逆に言えば制作側が勝手に膨大なページ数の提案をし続けたことが、肥大化したサイトが多くなっているということにも繋がっているのだが。
![[ウェブページのデザイン事情・画像]](http://www.swany.ne.jp/minba/u/ni/uedamomoko.jpg) |
ということのようだ。4億円以上の資本を使い切って消えたそうだ。事実上の倒産。スタッフは給料はもらってないとのこと。連絡がつかないらしい。会社には債務者が押し寄せ、たまたま義理人情で出社していた社員が捕まり拉致されたとか。とにかくひでぇヤツらだ。 http://ameblo.jp/ideoraism/entry-10052273607.html
![[ウェブページのデザイン事情・画像]](http://www.swany.ne.jp/minba/u/ni/katayamasatuki.jpg) |
鳴り物入りで公開したサイトなのだから、もっとニュースになってもいいようなものだが、そういった情報もウェブ上には見当たらない。ただunselfの元スタッフのブログが数件あり、いずれも今年8月で書込みを中止している。うち、元unselfのCOOのブログでは自身が独立するためとのことでブログを終了。つまりこの時点で営業の執行責任者が退職しているということになる。まあ公開連絡窓口が株式会社USENとなっているので、コンテンツだけは何とか引き継いでくれることを期待しよう。
![[ウェブページのデザイン事情・画像]](http://www.swany.ne.jp/minba/u/ni/isibasigeru.jpg) |
動画・無料動画レッスンサイト unself[アンセルフ] がここ1週間ぐらいアクセスできない。ドメインのunself.jpの有効期限は2007/11/30 で状態はTo be suspended となっている。つまり廃止予定ということ。運営するMtcVisionのサイトにもこの件に関する情報は無い。1日に万単位でのPVがあるサイトとしてはユーザーに対しての説明義務があるはずだろうが、全くもって無責任なハナシだ。それに既に撮影とV編集を終了して掲載待ちのレッスンもある。こういった人たちに対しても何の連絡も無い。
![[ウェブページのデザイン事情・画像]](http://www.swany.ne.jp/minba/u/ni/marukawatamayo.jpg) |
名刺にURLを印刷して、社長が会合で名刺交換したときに自慢できるようにウェブサイトを作る。といった目的でのウェブ制作の仕事もある。
しかし、社長が会合でいくら名刺を配っても、その名刺を見てアクセスしてくる人はいない。なぜなら社長は今までもらった名刺を見てそこに記載されたURLにアクセスしてみたことが一度も無いからだ。
![[ウェブページのデザイン事情・画像]](http://www.swany.ne.jp/minba/u/ni/hukiisikazue.jpg) |
会社案内のページにどうしても「社内規則六か条」を載せたいという社長。そんなものは絶対に誰も読まないと感じるウェブ制作者とその社長以外の全人類ではあるのだが、ウェブ制作費を払うのはその社長だ。その社内規則六か条がよっぽどひどい内容であったにしても載せざるを得ないだろう。
「見る人の立場に立ってデザインした」なんていうのは後付けのキレイゴトであり、普通はクライアントのほうを向いている。だからユーザーフレンドリーにはほど遠いサイトが沢山あるのだ。
![[ウェブページのデザイン事情・画像]](http://www.swany.ne.jp/minba/u/ni/naitodaisuke.jpg) |
広告メールや、どうしてもデザイン的な処理が必要な場合を除いては、やはりHTMLメールは避けるべきだろう。とにかくケータイで受信すると、反映される部分とされない部分があり、これがキャリアや機種によって様々なようでもある。受信した側は迷惑混乱するわけだ。
受信者が必ずPCで見ると分かっている場合を除いてHTMLメールは使わないほうが良い。特に文字を大きくしたり色をつけたりするだけならば、そのへんは文章力でカバーしろってもんだ。文字というものは、色や大きさに関係なく、相手に情報が伝わるようにできているのだ。
![[ウェブページのデザイン事情・画像]](http://www.swany.ne.jp/minba/u/ni/hatoyamayukio.jpg) |
昔は通信のトラフィックやPCのディスク容量を考慮して、メールは短く簡潔に!なんてことが言われていたが、今ではやはりケータイで読む人を考慮して短く完結に書くべきであろう。
とにかくケータイの小さな画面で長文を読むのは面倒だし、引用部分と本文の判別もしずらい。さらにその引用部分がやたらと長いのも迷惑だ。最悪なのはメールの尻に今までのやりとりが全て引用としてくっついているもの。これが過去の引用履歴と気付かずに読んでしまうと止めども無く難解なメールに思われるのだ。引用も必要最低限に!ということだ。
最近ではメールをケータイで送受信する人が増えている。そういう意味でも文章はできるだけ短く完結に。なるべく行数を減らしてスクロール量を少なくしてあげることが大切。相手の名前を件名や宛先に日本語で入れてしまうことで、本文には相手の名前を書かないで済ませるのも有効だろう。
文章表現が「ですます調」で冷淡な感じがするとか、命令されている気分だ、なんて言ってる人は、「誤解の無い必要最低限の文章でより早く的確に情報を伝える」というビジネスメールの本質を理解していないだけだ。長くてくどい情緒的な文章よりマシである。
メールは文章として記録に残るので、微妙なジョークや放送禁止用語も避けるべきであろう。もちろんそういった内容が通用する相手と分かっていれば書いても構わないが、通常のビジネスメールでは、やはり避けたほうがよい。また、どういった人が参加しているか分からないメーリングリストでは尚更禁物だ。
送信する相手の素性が分かっていない場合の、政治や思想、宗教に関連する意見やコメントも避けたほうが良い。 ブログやSNSが炎上するのは、こういった意見やコメントに端を発しているケースも少なくないようだ。
メールは文章として記録に残る。このことを注意しておかないと後々ややこしいことになるので気をつけたほうが良い。 例えば仕事に対する己の心境みたいなものは書かないほうが良い。心境や気分なんてもんは、時間とともに刻々と変化するものであり、心境を読ませれたほうにしても、だからどうする!?という気分にしかならないだろう。
どうしても書きたいのであれば、相手が見ることができない非公開のブログか何かで密かに書けばいい。どうしても相手にこぼしたいのであれば電話でさりげなく伝えたほうがいい。あとで自分で読んで「しまったぁ。。」と思わないようにしよう。
ウェブサイトのシェイプアップリニューアルが増えてきている。会社の情報を漏れなく掲載したサイトでも、実際にアクセスの多いページは限られているし、ほっとんどアクセスの無いページも少なくはない。
公開する側としては自社の情報を出来るだけ多く載せたいというのも心情。誌面に限りが無いというウェブの優位性も活用したいという気分にもなるというもの。
しかしユーザー側の立場で考えれば、実際に必要な情報というものは限られている。そこに注力して内容の濃い、魅力的なコンテンツ作りをするべきなのだろう。
.