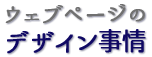2010年1月
| ●忘れない方法 2010.1.31 | ||
| 記憶の揮発性の高い人がいる。忘れん坊と呼ばれる人たちだ。ではどうすれば忘れないようになるのか? まずは出来事を単に聞き流さない、見ただけで終わらないようにすればいい。何か覚えておきたいことがあったら、それを単に記憶するのではなく、 何かを関連付ける。そのものに似ているもの、相反するものを頭の中で捜す。またはアレンジして似ているものを自分で創作する。と、そんなふうにして個々の記憶に横のパイプを何本かくっつけて逃げないように固定する。これで揮発はある程度押さえられる。 | ||
| ●ページデザイン 2010.1.29 | ||
| どう見ても分かりにくいページというのがある。そしてその分かりづらさから一瞬で離脱する閲覧者も少なくないはず。 ただしそういう閲覧者は、いちいちサイト主宰者に「分かりにくいぞ!」なんて伝えない。いやなら見なけりゃいいわけで、そういう意味ではネガティブな 意見が入手しづらいというのもウェブページの盲点だったりする。 | ||
| ●睡眠時間 2010.1.27 | ||
| 睡眠時間の短さを自慢するやつがいる。ばかではないのか。仕事ができる人間はさっさと時間内に終わらせ充分な睡眠をとり、翌日も集中力のある状態で仕事に挑むわけだ。そもそも毎日3時間しか寝てないんじゃ普通は病気になるだろう。ナポレオンじゃあるまいし(ナポレオンは毎日昼寝を欠かさなかったという説もあるが)。といっても高齢になるに従い長時間の睡眠ができなくなってくるというのも事実ではあるらしいのだが。 | ||
| ●キャパ 2010.1.25 | ||
| 2種類いて、1つは、自分のキャパ以上の仕事に手をつけてしまい、あとから収集がつかなくなる人。もう1つは、安全を見すぎて常に自分のキャパ内に収まるようにしているために崖っぷちを体験しないがために底力がつかない人。最大公約数で走り続けるのは難しいものだ。 | ||
| ●メール 2010.1.23 | ||
| さて始めるか!とパソコンを起動すると、「お、メールが来てる」となる。大抵は来ているのだから驚くことではないのだが、忙しい時に限ってたくさんくる。しかもレスを必要とする内容のものが多い。「ま、いいや、あとにしよう」とここでスルーすると、あとからタイヘンなことになるので、無理してでもその場でレスしておかねばならない。そうしないと「レス遅いやつ」「フットワーク悪い」「カメ」とか陰で囁やかれるようになる。 | ||
| ●やるやる 2010.1.22 | ||
| やるやると言いながら結局やらない。理由は「忙しいから」。他の仕事が次々と入ってきて手が回らなくなる。仕事がたくさん入ってくるのは良いことであり、能力や信頼があるから仕事も入ってくるというもの。しかし、そこまで見越して、自分がこれからどのくらい忙しくなるかをある程度予想しながら「やる」と言うようにならなければいかない。本当は。 |
| |
| ●威張る 2010.1.21 | ||
| いつも威張ってる人間は総じて小心者で寂しがりやだ。寂しいのを紛らわすための行動が「威張る」という自分の存在を主張して周りに自分を注目させることになる。または基本的に威張ることでしか自己主張できないので、威張っても聞いてくれる人間がいないと人並み以上に寂しく感じるようだ。まあ、周囲から信頼されていて権威や実績があって仕事のできる人間は、そうそう威張った態度はとらないものだ。敗北や失態を恐れるための先制攻撃が「威張る」というかたちになって現れているのだろう。 | ||
| ●こんなコトで客を逃している【その7】 2010.1.19 | ||
| クロスプラットフォームされていないページ。多くのサイトはWindows+IEの環境でチェックしながら作られている。しかしFireFoxの利用者は10%、Macユーザーは5%、その他SfariやCromaの利用者も微増している。例えばFireFoxで見た場合に価格表示が隠れてしまう、とかレイアウト全体がバラバラになって何が書いてあるのかわからない、といったページをたまに見かける(それでも少なくなってはいる)のだが、一通りの異なった環境でのチェックは必要。Windows+IE以外の環境で正しく表示できないというだけで、20%の客を逃していることにもなる(乱暴な計算だが)。最も多いのがMacで見た時に「¥」が逆スラッシュになっているというものだろうか。 | ||
| ●こんなコトで客を逃している【その5】 2010.1.17 | ||
| 送料一覧に「島嶼地域」が書かれていない。または「島嶼地域は別途相談」という記載。これは他の地域に住んでいる人には関係ないことであるのだが、島嶼地域に住んでいる人にとっては「送料が明記されているサイトがあまりないのでネットでの注文は制限されてしまう」ということになる。この部分をきちんと表示することで、同じカテゴリー内での島嶼地域在住の顧客を全てゲットできるかもしれない。また島嶼地域の表記が無い場合、仮に小笠原村の客が「うちは東京都なのだからサイト表記の東京都の送料でいいんだよね?」と突っ込まれる可能性もあるわけだ。とはいえ実際に島嶼地域からの注文は全体の1%にも満たないだろう。もちろん商品にもよるが。 | ||
| ●こんなコトで客を逃している【その3】 2010.1.15 | ||
| 定価やメーカー希望小売価格をわざわざ表示して、それに斜線を付けたり、割引率を表示したりして激安感を表現する。これが同じサイト内の商品を10個買えば安くなるとか、まとまった数を売り続けた後の値下げであるとか、会員価格の表示というのであれば効果は期待できるだろう。しかしメーカー品(デジカメとかPC周辺機器、家電製品など)は他のサイトでも同じ製品を売っているわけだし、買うほうだって他のサイトとの価格を比べながら選ぶのがデフォルトだろう。それを「あたかも安く見せようとする小細工」は過剰表現としての印象を与えて客が「引く」ことにも繋がる。素直に販売価格のみを表示することで、それとなく「信頼感」を与えることにもなる。 | ||
| ●こんなコトで客を逃している 2010.1.13 | ||
|
ネットショップというのは実店舗と違って客が商品を購入する経過を見ることができない。だから客を逃していたとしても、その数や原因を把握することは難しい。中にはちょっとした細かい部分での表記や表現が誤解を招き客を逃がしていることもある。その例をいくつか紹介する。 【その1】 決済のところに「佐川e-コレクト」と表示されている。e-コレクトとはセールスドライバーによる代金引換やクレジットカード、電子マネー、デビットカード決済などを含めた「玄関でお支払いできる」決済のことである。しかし一般的には「e-コレクト」と聞くと、専用のカードとか、何か特別な決済方法と勘違いされがち。「なんだ代引きは無いのかぁ。」と去っていく客がいる。 | ||
| ●早く死ね 2010.1.12 | ||
| 自分では絶対に手足を動かさず指図だけをする。結果が悪いと怒りまくり、ではその結果が自分で予測できたのかと言うとそうではない。指図したほうの否は絶対に認めず責任もとらなければ謝罪もしない。というような人間は周囲から「早く死ね!」と思われているのだが、実は本人見た目以上に必死で生きている。 |
| |
| ●改善の余地 2010.1.11 | ||
| どんなに優れた人間が作った制作物でも、必ずどこかに「改善の余地」はある。それがなかなか見いだせないようなものが「芸術」と呼ばれるのだろう。 | ||
| ●話を聞く 2010.1.10 | ||
| 人の話を聞ける人間と聞けない人間がいる。後者は人が話をしている間は次に自分が何を話すかということだけしか考えておらず、そういう人間同士の会話は情報交換でもコミュニケーションでもなく、単にストレス発散ごっととなり、建設的な成果は生まれない。 |
| |
| ●言いたい事 2010.1.9 | ||
| 言いたい事は沢山ある。それを全て相手に分かってもらいたい。しかし相手にしてみれば、一度に沢山の事を言われてもワケが分からない。往々にして言いたい事を言い過ぎたがために全く相手に伝わっていないということがある。自分の言いたい事を言うのではなく、相手が理解できる範囲に要点だけを抽出して、シンプルにアレンジしてから伝えるべきである。多過ぎたるは及ばざるに劣るのである。そしてべらべらと言いたい事を言いまくった人間ほど「あの時言っただろう!」などと宣うものだ。そんなもん全部覚えてるわけねーだろ。 | ||
| ●アクセス数 2010.1.7 | ||
| アクセス数が減ってくる。と、その原因は「更新頻度が低いから」または「SEO対策が足りないから」と思う人が意外にも多い。確かにそれらは要因に一部かもしれないが、もっと重要なことは「コンテンツがつまらない!」ということなのだ。期末試験の成績が悪いのは「ヤマが外れた」とか「前の晩徹夜して寝不足だったから」とかではなく「勉強が足りない!」ということなのだ。 | ||
| ●アフォーダンス 2010.1.5 | ||
| これはちょいと小難しい概念のようだ。元々は「環境がその中に生息する生物に対して与える意味」というようなものだが(これだけでもイメージするのが面倒なのだが)、これがユーザーインタフェースやデザインに対して使われるようになってきた。つまり上記の「環境」が、インターネットを含めたコンピュータのハードウェアやアプリケーション、OSとなり「ユーザーインタフェースやデザイン」がその入口であって、利用者は上記の「その中に生息する生物」ということになるのだろう。ある意味「ただぼうっとコンピュータを使うのではなく、その中に意義を見いだせ!」と言っているようにも思える。 | ||
| ●フォークソノミー 2010.1.3 | ||
| サイト上の情報に利用者がタグを追加していくことを「フォークソノミー」と言う。例えばニコニコ動画やPixivがこれに当たる。Wikipediaやはてなブックマークも基本的な考え方はフォークソノミーである。ある意味大衆の叡智としてボトムアップ型の検索システムでもあるのだが、情報の信憑性やクウォリティが落ちるという問題もある。特にオリジナルを作れない人間にとっては自分を主張し、注目を集める恰好の場ともなってしまうわけだ。 | ||
| ●木登り 2010.1.1 | ||
| 木登りをする子どもが少なくなった。人間は動物として子どものころには木登りをしないといけないようにできている。登る技術とかコツとか体力とか、それは大して重要ではない。どのくらいの枝が自分の体重で折れるのか?朽ちた枝は外観からどう判断すれば良いか?どのくらいの高さから落ちるとどのくらい痛いのか?ということを経験することが重要なのだ。これを子どものころに養っておかないと、大人になってから危険を察知する能力が低くなり、危機の限度が判断できなくなるのだ。 | ||
.