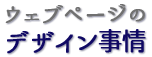2011年1月
| ●聞きかじった知識 2011.1.30 | ||
| よくあるのがウェブの作り方や運営の仕方についての聞きかじり論だ。今やメディア上のこのような情報が溢れているのだが、それをあたかも持論のようにデジタル弱者に対して説明する人間の多いこと。そこまで言うなら、あんたいったい何件のウェブサイトを構築、デザイン、管理、運営してきたってわけ?なのだ。理屈ばかりで実践経験の無い人間の聞きかじり論は、ウェブに限らず、どんな業界、業種においても机上の空論だ。何ごとも現実はもっと複雑で理屈では説明しきれないことが沢山あるわけだ。 | ||
| ●好み 2011.1.28 | ||
| デザインなんて「好み」だ。などと言う人がいる。であれば食べ物だって「好み」だろう。それでも行列のできる店もあれば、明らかに美味しくない店もある。デザインも同じだ。 | ||
| ●ダミーテキスト 2011.1.27 | ||
| 制作途中のサイトでテキストの原稿が未入手のときにYahoo! Japanのニュースのテキストとかをダミーとかを入れることがある。もちろん公開ではなくクライアントだけに見せるものだ。ところが「ここの文章が違っている」と真面目にコメントされることがあるのだ。説明するのがメンドクサいので最近は入れないようにしている。 |
| |
| ●長生きしよう 2011.1.26 | ||
| ネットショップの商品紹介のキャッチで「100歳まで生きられる!」とか「〜を使って長生きしよう!」というのを見かける。決してそういった目的の商品ではないのだがなぜか?と思っていたのだが、どうやらキャッチを考えた人が比較的高齢であるということが分ってきた。自分の寿命の終わりが見えてきたので自分に言い聞かせているというわけだ。 | ||
| ●コンサルとか 2011.1.24 | ||
|
無責任に説明だけをしてお金を貰うというのが最もリスクの少ない商売だ。といっても、そういったコンサルや診断士的な肩書きで能書きだけを語ってる自称「先生」も沢山いるのだが、やはり実戦経験が無い人間はすぐにバレる。なぜバレるかというと、 ・自分が関わっていない成功例の紹介が多い ・何かと断定的である ・使い回しであろうプレゼン資料がよくできている ・具体的な質問に対して抽象的な答えを返す といったところだろうか。 | ||
| ●情報はがめつく集める-2. 2011.1.22 | ||
| 同じことがウェブサイトにも言える。ウェブサイトを開設しようとして色々と情報を集める。雑誌や書籍を読む、ウェブから情報を集める、既にネットショップで成功している人から話を聞く、経営コンサル、中小企業診断士にも聞いてみる。企業主催のセミナーや勉強会に出席する。と、当然のことながら色々と異なる事例やアドバイスが溢れてきて収拾がつかなくなり、何をやったらいいのかが分らなくなる。 | ||
| ●手抜きメール 2011.1.19 | ||
| ビジネスメールは自分の考えや思いを伝えるものではなく、受信した相手が的確に作業ができるようにする指示書である。しかし実際には思いを伝えただけで受信したほうは全くわけが分らないというメールも少なくない。最初はきちんと指示をしていても、馴れてくると主語が抜けたり具体性に乏しかったりと、段々と手抜きになっていくケースもある。そんな時は、例え内容を理解できたとしても「どのファイルのどの部分を修正するのか具体的な指示をください」とレスする。そうしないとクセになって段々と手抜き度合いがエスカレートするからだ。 | ||
| ●CI-1 2011.1.17 | ||
| ウェブデザインをしていると、成り行き上CIをやることもある。といってもクライアントは中小企業や個人事業主なので、会社のロゴマークをデザインして使用マニュアルを作る程度ではある。そして多くのクライアントから「もうちょっと横長にならないか?」「もっと短くならないか?」という要望が来る。これは目前の印刷物や販促品に使う際にそのほうが扱いやすいためだ。もちろんそういった要望には対応しない。 | ||
| ●ネット上での動画のメリット-キーワード効果 2011.1.15 | ||
| Google では動画の中に含まれる音声、また画像に写っている文字を、それぞれキー ワードとして認識、判別する技術を検索結果に反映させているとのこと。これは理 論上 1 本の動画で多数のキーワードを一気に埋め込むことになる。また Google の 画像(静止画)検索では、YouTube にアップした動画のキャプチャ画面を検索結 果に反映させるようになった。 | ||
| ●ネット上での動画のメリット-被リンク 2011.1.14 | ||
| 動画を YouTube などの動画共有サイトにアップしすることで、動画共有サイトか らリンクされる事が可能になる。また1つの動画共有サイトにアップすることで、 他の複数の動画サイトにリンクされることもある。いずれにしても動画をアップす ることでの被リンクの効果は大きい。 |
| |
| ●ネット上での動画のメリット-滞在時間 2011.1.13 | ||
| 一度動画を見てしまうと、例えつまらないものでも最初の 5 秒ぐらいは見てしまう。 テキストの場合はつまらなそうな(文字がいっぱい書いてあって読むのが面倒クサ そうな)ものは一瞬で他のページに移動してしまう。ここでの 5 秒と一瞬の差が積 み重なれば大きい。もちろん動画の内容が見た人が面白いと思うものであれば滞在 時間はもっと稼ぐことができる。 | ||
| ●人はなぜ動画を見るのか-2 2011.1.11 | ||
| ◎動いているものは自然に見てしまう: 人間に限らず動物は動いているものに対して自然に目が行く習性を持つ。これは進 化の過程で敵、餌、仲間を認識して次の行動に移るために必然的に身に付いたもの。 止まっているものに対して動いているものの注意を煽るパワーは何倍にもなる。 | ||
| ●人はなぜ動画を見るのか-1 2011.1.10 | ||
| ◎文字は能動、動画は受動: 文字を読むという能動的行為は、それなりに労力を要する「作業」。これに対し動 画を見るということは、入ってくる情報を受身で認識するだけ。テレビは見る行為 と本を読む行為とではどっちが楽かということ。基本的に人間は楽を好み、字を読 むのは嫌いな生き物である。 |
| |
| ●心にもないこと 2011.1.9 | ||
| 手書きの文章では思ってもいないこと、心にもないことを書くというのは難しいかもしれない。普通に書けばその時に考えていること、思っていることが自然と文章になってアウトプットされるであろう。これがメールとなると意外にもカンタンだ。もちろん考えながらタイプする場合にはカンタンではないかもしれないが、ビジネスメールの多くはひな形のコピペである。「このクソ野郎が毎回ムカつくこと言いやがって!」と思いつつも、ひな形をコピペして「本当にありがとうございました」と一瞬で書くことができるわけだ。便利なものだ。 | ||
| ●ドメイン. 2011.1.7 | ||
| ドメインメームサーバのことではない。いわゆる「立ち位置」という意味でのドメインなのだが、これを理解していない経営者が意外にも多い。昨日まで重量挙げをやっていたアスリートが、いきなり明日からシンクロナイズドスイミングをやろうたって上手くいくわけが無い!と言えば、分りやすいと思うのだが、これに近いことにトライしている経営者のことを「ドメインが違うだろ!」ということになる。何ごともトライするのは良いことなのだが、経営である以上は、ある程度は成功する確率を試算しないといけないだろう。 | ||
| ●確実に滅ぶであろうハガキの年賀状 2011.1.5 | ||
| 新年の挨拶は100%メール。という高校生も少なくないようだ。仮にハガキを出すときには予め「出していい?」とメールするそうだ。ハガキの年賀状を出すと相手もハガキでレスしなければならないというプレッシャーを与えることになり、しかも50円というコストが発生し、お互いに住所という個人情報を交換することになるからだ。こういった世代が大人になるときに、会社の風習として何通かハガキを出すことはあるにしても、ハガキの年賀状は確実に無くなるだろう。 | ||
| ●下請け 2011.1.3 | ||
| 製造業に限らず、ITでも大手から下請け、さらに孫請けという構図が成り立っていた。しかしこれがリーマンショック以降崩れつつあるようだ。外注するほうもコストがよりシビアになり、今まで発注していたところに毎度発注するということはせず、毎回最もリーズナブルな外注先を捜すようになる。当然のことながら割高なところには仕事は来なくなる。問題は価格競争が激化して、採算のとれない価格がスタンダードになってしまうということだ。 | ||
| ●テレビが見られなくなった理由 -7 2011.1.2 | ||
| ◎コンテンツの重要性を軽視: ハイビジョン放送、ブルーレイ、3D テレビなどの技術は開発したものの、コンテ ンツが伴っていないために普及しない。当たり前のことだがコンテンツの作り込み やクウォリティにもっと注力すべき。YouTube に掲載された動画をスタジオの芸 能人と一緒に紹介するなどという番組はやめるべき。 |
| |
| ●テレビが見られなくなった理由 -6 2011.1.1 | ||
| ◎スピードの遅さ: ニュースやスポーツの結果などは逐一インターネットで見ることができるが、テレ ビではその番組が始まらないと見ることができない。ネットで分かってる結果試合 をテレビのスポーツニュースで見る必要はない。 | ||
.